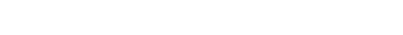小中合同ロードレース大会は中止となりました。
1月26日(水)の本番に向けて頑張っていた『小中合同ロードレース大会』が、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を受け、安全な開催が危ぶまれるため【中止】といたしました。
子供たちはこれまで昼休みにも黙々とグラウンドを走るなど、とても頑張っていましたので残念です。この頑張りをしっかり次へと生かしていってほしいと思います。
小中ロードレース大会の顔合わせ
1月14日(金)、小中合同ロードレース大会に向けて、小学生と中学生の顔合わせがありました。
小値賀小学校では、同じ校舎の中学生と一緒にロードレースの練習に取り組みます。

小中学生を12の縦割り班に分け、中学生のリードの下、自己紹介やめあて決めをしました。




初めて対面する中学生に緊張しながらも、グループでまとまって準備運動まで行いました。




1~3年生と中学生が内側、3~6年生外側を走りました。1~3年生には中学生が一緒に、優しく声をかけながら走ってくれました。
本番は1月26日(水)。それまで何度かこのように、小中学生が交流を深めながら練習に取り組みます。
優しいお兄さん、お姉さんに囲まれて、小学生のはにかみながらも、笑顔で活動する姿が印象的でした。
児童代表発表がありました。
1月14日(金)、2・4・6年生の児童代表発表がありました。



2年生の代表:「自学ノートを頑張る、6年生のためにそうじを頑張る」
4年生の代表:「素敵なリーダーになるために、下級生に優しい声掛けを頑張る」
6年生の代表:「下級生のお手本になる、卒業に向けて小学校生活を楽しむ」
全校児童を前に、堂々とした発表ができ、まさに代表児童として頑張りました。
素敵な3学期を過ごすことでしょう。
3学期始業式
1月11日(火)、3学期の始業式がありました。



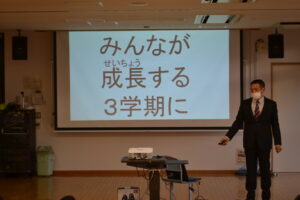
1月は「いく月」、2月は「にげる月」、3月は「さる月」なので、一日一日を大切にして縦割り班掃除やあいさつを頑張っていこうという話がありました。
長い冬休みでしたが、子供たちの明るい笑顔が小値賀小学校に戻ってきました。
令和4年もよろしくお願いします。
2学期終業式
12月24日(金)、2学期の終業式がありました。


校長先生からの話では、通知表での子供たちの成長について話がありました。それぞれの努力、頑張りについて紹介がありました。
また、縦割り掃除での頑張り、あいさつの頑張りが光っていたという話もありました。

その後、児童代表の発表がありました。
1年生の代表は、漢字の学習を頑張り、楽しく漢字を覚えるため声に出して覚えたことを話してくれました。
3年生の代表は、一輪車の乗り方を友達が一生懸命に教えてくれた喜びを話してくれました。
5年生の代表は、宿泊学習での魚さばき、かんころもちづくりを頑張ったことを話してくれました。


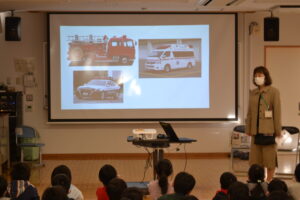

最後に、生活指導主任から、冬休みの過ごし方について話がありました。
規則正しい生活、お金の使い方、3つの車に関わらないようにとの話がありました。
どの子も楽しい2学期だったという感想を持っていました。
令和4年1月11日にも、このかがやく子供たちの笑顔が見られることを楽しみにしています。
今年も何かと本当にお世話になりました。
よいお年を。
クリスマスプレゼントをいただきました!
12月20日(月)に「ふるさとの味・かーちゃんの味つたえよー会」の方々からクリスマスプレゼントをいただきました。本来ならクリスマス会を開かれるということですが、昨年につづき今年も学校からの配付となりました。一人一人に担任から配られました。


みんなとびきりの笑顔で喜んでくれました。
毎年本当にありがとうございます。
English Day
12月17日(金)、小値賀町小中高一貫教育の合同行事の一つ、「English Day」がありました。小学5年生から中学1年生までの児童生徒で縦割り班を組み、英語に親しみました。





小学校5,6年生の担任、中学校の英語の先生が5つのグループに関わり活動しました。
簡単な自己紹介、スリーヒントクイズなど小中学生が和気あいあいと活動しました。ALTの先生からは、オーストラリアでのクリスマスの様子を教えていただきました。
「難しい所もあったけど、楽しかった!」という感想もあり、英語活動を楽しんだ小値賀の小中学生でした。
人権集会がありました。
12月14日(月)、朝の時間に『人権集会」がありました。昨年度までは、小中高一貫教育として行っていましたが、発達段階に応じた指導をしたほうが子供たちのためにより良い指導ができるということで、今回はクラスごとでの人権学習となりました。低・中・高学年でテーマを決めて学習しました。
まず最初に校長先生からの話です。




人権とは「楽しく生きるためにまもられるもの」であり、学校でもこれが守られないこともあること、守っていかなければならないことについて話がありました。




1・2年生は「いいところみつけ」をして、自分ではわからなかった自分のいい所がわかりました。3・4年生では、「ちがい」について学習し、違いがあるからこそいいことを学びました。5・6年生は男女の差について、日頃気付きにくいものもあることに気づきました。
この学習を通して、「楽しく生きるために守られるもの」がわかり、よりよい学校にしていこうという気持ちが高まりました。
かんころもちづくり<5年生>
12月7日(火)、分校のある大島へ『かんころもちづくり』に行きました。




小値賀の名物ともいえるかんころもちですが、作るのを手伝ったことがある子は数人で、中には食べたこともない子もいました。ここのかんころもちは、餅に干したサツマイモ、砂糖にショウガ、ゴマを入れるそうです。こねているときのいい香りに、早くも「食べたい!」とこどもたちの声があがっていました。



あつあつのかんころもちを丁寧に成形しました。簡単そうに見えて意外と難しいものでした。

時々、ネコと戯れながら…

たくさんの、出来上がったかんころもちを抱え、船に乗って帰りました(温かいお見送りもありました)


なかなか個性的な形もあるますが、心をこめて作りました。乾燥させ、あとで持ち帰ります。
とても貴重な体験ができました。ぜひ、小値賀の伝統を引き継いでいってほしいと思います。
この活動にたくさんの方々の協力がありました。
しっかり感謝の気持ちをもっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
4年社会科見学(小値賀の歴史)
12月6日(月)、晴天の下、「小値賀の先人たちに学ぶ」社会科見学がありました。教育委員会の学芸員、小値賀公民館長の方々に説明していただきなながら、町内の様々な史跡を案内してもらいました。
まずは「建武新田」の見学です。



今から700年ほど前、二つの島だった小値賀の海を埋め立てた新田を見学しました。昔海だったところを埋めたてて17ヘクタールもの新田を作ったということを説明していただきました。当時の海岸だったところを考えたり、田の様子を観察したりしながら様々な発見がありました。


当時からある貯水池と水門も見学しました。







次は、子供たちも楽しみにしていた『膳所城(ぜぜじょう)跡』です。
700年以上前の城跡で、お堀の様子、船着き場の様子などを見学し、当時の城がどのようなものだったのか想像を膨らませました。ずいぶん昔のものですが、その当時の人が考えていたことややっていたことがよくわかりました。神社後も見学しました。


新田開発のために犠牲となった牛たちを供養するために建てられた『牛の塔』を見学しました。
この下には小さい石7万個ほどにお経が書かれて納められていると聞いて子供たちはびっくりしていました。


最後に『経崎山』に行きました。新田を見下ろすような丘に立った墓石がありました。いまだに誰のお墓かわからないが、大きな力がある人だったのではないかという説明を聞き、「わからないことが多いな。」という感想を持つとともに、わからないことを想像し、推理することへ楽しみを感じていました。
子供たちはこの一日で、様々な小値賀の歴史を知り、先人たちのすさまじい努力を実感できました。
これからも、今日の記憶は残り続けていくのではないでしょうか。
昨日より、小値賀を好きになったことでしょう。
- 小値賀町立小値賀小学校

お電話