SAKE 〜今と昔〜
3年小金丸 香
お酒の作り方
◎日本酒
←福田酒造パンフレットから
◎焼酎・・・原料を発酵させ、そのアルコールを含んだ発酵液自体を酒としたもの。日本国有の蒸留酒として、世界に誇るもの。
福田酒造パンフレットから→
<例>甲類焼酎
①甲類焼酎は蒸留酒
↑”クセのなさ””のみやすさ”
②製造工程の違いで”甲類”と”乙類”にわかれる。連続式蒸留機によって何回も繰り返す。
〜れきし〜
①14世紀、沖縄に種の東洋の蒸留酒(焼酎)がきた。
②海賊が焼酎を含む外来酒を日本に運んだ。
③交易品の中には特に、朝鮮産の焼酎が含まれており、日本に入ってきた。
|
年代 |
できごと |
| 紀元前 | 古代エジプトで蒸留機「アランビック」を発明 |
| 明治28年 | イギリスの「連続式蒸留機」が日本に輸入 |
| 明治43年 | 新式焼酎(甲類焼酎)の登場 「日の本焼酎」が発売される→「ハイカラ焼酎」の登場 技術革新により大量生産が可能になり、出荷量増える |
| 大正期 | 米を使わない酒「焼酎」として空前のブームに 米騒動が原因で、米を使わない酒「焼酎」が脚光を浴びるようになった また、第一次世界大戦のためアルコールの医薬的、軍事的、科学的需要が増大 連続蒸留(甲類焼酎の製造方法)の技術が飛躍的に進歩する |
| 昭和初期 | 軍事用アルコールの需要高まる日中戦争、太平洋戦争が原因 |
| 昭和24年 | 酒類の配給制廃止焼酎業界の活動が勢い増し始める |
| 昭和40年頃 | 国産ウィスキーの台頭→焼酎の生産が減少(技術革新期) |
| 昭和52年 | 名実共に「第三の酒」になる(ビール、清酒、そして焼酎) 白色革命→アメリカのホワイトスピリッツブームが、日本に影響する各社新製品を発売する |
| 昭和59年 | 第2期光厳時代 酎ハイブーム→甲類焼酎の需要高まる |
| 昭和60年 | 焼酎カクテル流行→甲類焼酎の需要さらに高まる |
| 現在の焼酎 | 平成8年出荷数は400000kl 大衆のお酒として定着 |
★ひとくちメモ★
分類
醸造酒・・・日本酒、ビール、ワインなど
蒸留酒・・・焼酎、ウイスキー、ブランデー、ウォッカなど
混成酒・・・リキュール、甘味果実酒、みりん、混合清酒など
◎福田酒造をたずねて
<インタビュー>
Q昔、今の酒づくりの違いは?
A基本的には同じ。今:米をたく 昔:米をむす
Q昔の酒の味は?
Aにごった酒で香りが悪かった。
Q酒造りでつらいことは?
A冬の朝、寒いのがつらい。
Q日本酒と焼酎はどっちがはやく作られた?
A日本酒!1番古い。
◎作業の様子


↑箱づめをしているところ 「がんばってます!」
〜感想〜
・ラベル貼りや箱づめが楽しくできた。でも、何時間もしていたら、きついだろうなと思った。今回、福田酒造に行って、質問などを積極的にできなかったので、今度は、積極的にどんどん質問していきたい。
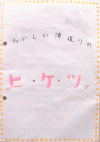 ←← くわしく見たいところをクリックしてください
←← くわしく見たいところをクリックしてください
◆感想をおくって下さい◆